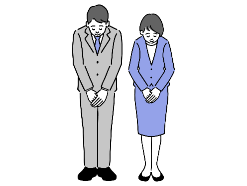期間工として働く場合、そして退職した場合、税金の支払いはどうなるのでしょうか。税金にはいくつか種類があり、時期によって手続きや支払金額が変わります。年末調整のタイミングや住民税の請求などで後々慌てないために、抑えておくべきポイントや注意事項をお伝えします。
期間工として働いている間の税金
期間工として働いている間、税金は給与から天引きされる形で納税されます。会社が支払ってくれる主な税金は、所得税、年金、健康保険料、住民税の4つです。
所得税は、家族がいるかいないかなど、個人の状況に応じて金額が変動します。さらに税率は課税所得額に応じて決まるので、支払われる給与が多ければそれに比例して納税額は多くなります。国税庁のHPで所得税を算出する計算式が確認できます。
課税所得金額とは、総所得から扶養控除や生命保険料控除など「所得控除」と呼ばれる控除金額をのぞいた金額のことです。大まかに計算をして会社が納税していますが、一年間の所得によって納税額が決まるため、年末調整で税金の戻りや追徴課税が発生します。
年末調整で気をつけること
年末調整は、毎月の給与から納税した金額が、1年間の給与と照らし合わせて正しいかどうか確認し調整するものです。11月~12月に雇用主のメーカーから年末調整の用紙を渡されますので、必要書類をそろえて提出しましょう。
年末調整で申告の対象となるのは、扶養する家族が増えたり減ったりした場合や、配偶者に収入があった場合、個人で掛けている生命保険などの支払いがある場合です。
申告の際には、支払証明書をそれぞれの会社からもらい、用紙に添付します。記入の仕方は用紙の裏に書いてあるので見ながら記入しましょう。それでも不明な点があれば、会社の担当部署で聞くと教えてもらえます。
生命保険のほかに個人で年金をかけていた方、住宅の火災保険料を支払っていた方などは、支払った金額が控除の対象になります。
12月の初旬に書類の提出期限を設定している会社が多いので、支払証明書は早めに手元に用意しておきましょう。保険会社に確認する際には、源泉徴収の添付書類であることを伝えると良いでしょう。
期間工を辞めた後、税金はどうなる?
期間工として働いている間の納税は、基本的に会社が行ってくれます。
では、契約終了後は健康保険料、国民年金、住民税は継続できるのでしょうか?
継続しないでそのまま放っておくとどうなるのでしょうか?
税金を収めることは国民の義務なので、収入があれば納税しなければいけません。ただし、期間工を辞めて収入がなくなった場合、所得税は発生しません。
期間工として働く際、入社時に健康保険に加入しますが、契約期間が満了してメーカーを退職するタイミングで健康保険証は返納します。その後、社会保険事務所の窓口へ行き、健康保険の任意継続をするか国民健康保険加入の手続きをとります。
もし手続き中に病院にかかる場合は自己負担になりますので注意しましょう。一旦医療費が10割負担になりますが、きちんと手続きを踏めば3割負担になるようお金が戻ってきます。領収書をもらっておきましょう。
年金については国民年金機構から届く通知で、年金支払期間やもらえる年金の確認ができますので、空白の支払期間があった場合はその期間の年金も納めるようにしましょう。
税金で注意が必要なのは、住民税です。住民税は、前年度の給与に応じた金額を翌年納税する仕組みとなっています。
期間工の契約が2年だった場合、1年目の住民税は給料から引かれますが、2年目の住民税は契約期間が終了した次の年に納税しなくてはいけないので、貯金をするなどして備えておきましょう。
住民税は、その年の1月1日に住んでいた地域(住民票のある地域)に納める必要があります。期間工になる以前に収入があり、その年の途中で入寮するなど住居を移転した場合は、以前住んでいた地域の住民税がかかることになります。
まとめ
期間工で働いている間は、会社が処理をしてくれるので税金の心配は不要です。収入に応じた金額が納税されますが、税金が戻ることもあるので、年末調整時に書類をそろえて手続きを行いましょう。
期間工の契約が満了すると、健康保険や年金は個人で手続きをしなくてはなりません。住民税の支払いも遅れてやってきますので、注意しておきましょう。
期間工のお仕事探しはこちらから